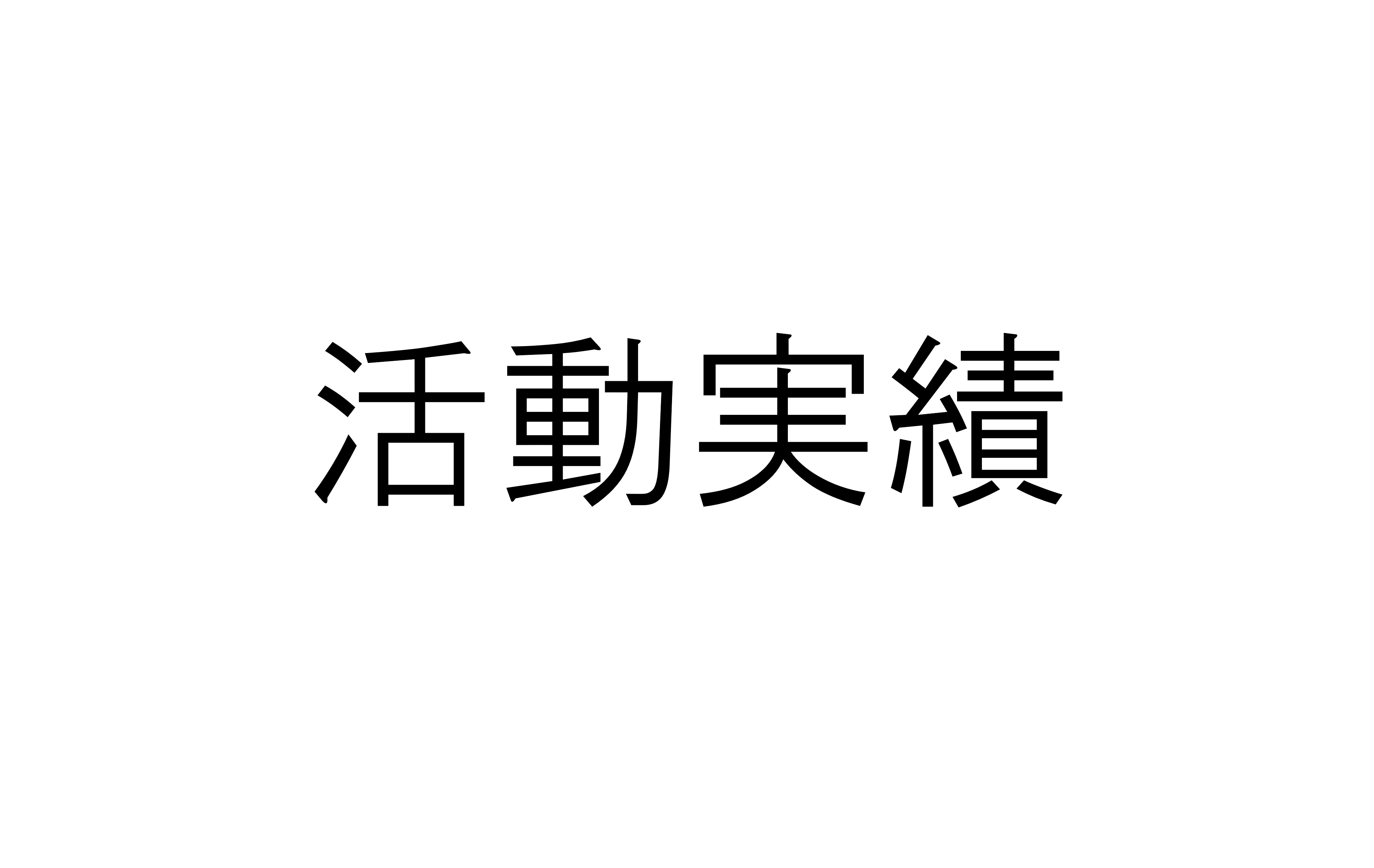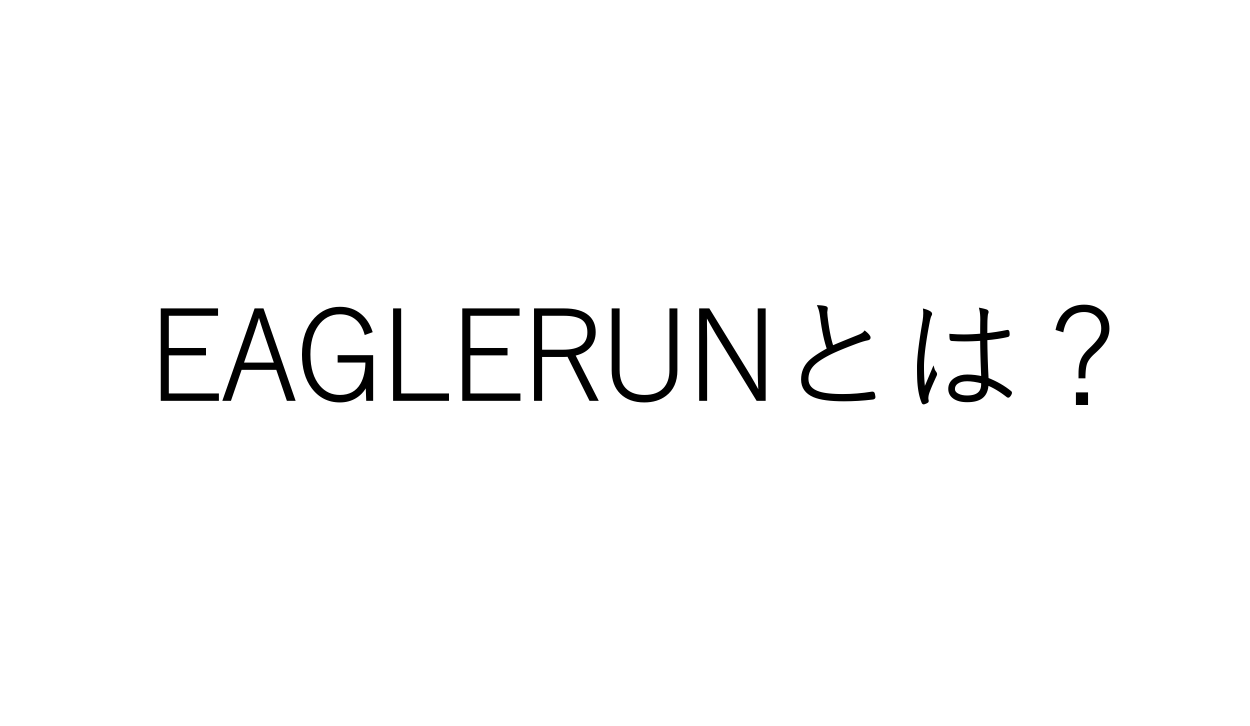目次 ・EAGLERUN RC TOP・平塚本部・EAGLERUN RC 開催日程・活動ブログ・過去のブログ
EAGLERUN RC 開催日程
※1週間前まで平塚競技場の予定が発表されないため、それより先の場所で確定していないところは「未定」となっています。
2月13日(金)18時30~20時00(平塚競技場)
2月15日(日)10時00~11時30(平塚競技場)
2月16日(月)17時30~19時00(平塚競技場前)
2月18日(水)17時30~19時00(平塚競技場)
2月20日(金)18時30~20時00(平塚競技場)
2月22日(日)10時00~11時30(未定)
2月23日(月)17時30~19時00(未定)
2月25日(水)17時30~19時00(未定)
2月27日(金)18時30~20時00(未定)
<集合場所>
・平塚競技場の場合:平塚競技場入り口(中央ゲート)
・平塚競技場前の場合:同平塚競技場入り口に集合してから下画像①地点のあたりへ移動
※①近くの坂へ移動する可能性がありますので、大幅に遅れる方はご注意ください。
・野球場下の場合:総合公園内野球場外の三塁側屋根下(下画像②地点)
<雨天時活動場所>
雨天時は上記指定の集合場所にお集まりいただいた後、時間になりましたら以下の屋根付きの走路に移動する可能性があります。
大幅に遅れる方はご注意ください。
・平塚競技場の場合:競技場入り口と①の間にある室内走路
・野球場下の場合:屋根があるため変わらず野球場下で活動

EAGLERUN RC 活動ブログ
【日々の様子を掲載】EAGLERUN RC平塚本部 公式Instagramはコチラ
2月12日
インフルエンザが流行っています。
皆さん気をつけてくださいね。
さて、先日の雪を経て、冬も少しずつ終わりが見えてきました。
昨日水曜メンバーとマーカーを12mずつなど一定間隔を4歩ずつで超えるストライド走を行いましたが、12月より明らかにストライドが出ていました。
間違いなく成長しています!
今月末からは「速い動き」がどんどん増えてくるので、それまでしっかりストライドを体に染み込ませましょうね!
2月5日
先週の日曜は私も一緒にやりましたが、きつかったですね~。
私たちは走るということを行い、やるからにはもっと速くを目指しています。
そこで必ず出てくるのが「このままで本当に速くなれるのか?」という疑問です。
本気でやっているほど不安に思うときも来るでしょう。例えば練習で良いタイムが出なかったときはそう思いやすいです。
その時はに危険なのは、思考を止めて盲信することです。
けっこうこうなる人は多く、その場合結果が出にくいばかりか、心を壊したり、将来自分の意見を曲げられない人になってしまいがちです。
大事なのは、自分が速くなるには○○が必要であり、この練習はそれを得る為に有効だ、と根拠立てて理解できること。
それは、自分の目的に合わない練習はしなくていい、ということではありません。
人間としての限界タイムになっている人以外は、皆が未熟を抱えており、不要な練習なんてないんです。
だからこそ、練習の意味を理解し、より自分が成長できるものに引き上げること、練習は何をやるか以上にどうやるかが重要だということです。
日曜の練習しかり、これができれば、これをすればもっと強くなれるぞ~と合理的に思える練習時間にしていきたいですね~!
1月29日
今週の日曜の話です。
日曜は荒川コーチ練習挑戦会ということで、フェーズ④にチャレンジします。
この練習の良いところは、練習にもなり、かつ現状の評価にもなるということです。
まず、このフェーズ④を設定タイム以上で完遂できた人は、かなりの確率で今年ベストがでます。
なぜなら、この設定は近年のベストタイムから算出された、「フィジカル・テクニックなどを全て使ってギリギリできるかどうか」のレベルに調整されているからです。
つまりそれが初回でできる人は、すでに設定が甘くなっている、つまりその根拠となる近年のベストタイムよりも速いタイム水準に自分がなっているということになります。
なので、楽にできればそれは素晴らしいことですが、タイムがオーバーしてしまったり、途中離脱の人も多く出てくると思います。
上記の通り、初回でできないのは全然問題ではなく、大事なのはそこから何を学ぶか。
肺が先にダウンしたなら心肺機能が足りない、乳酸が原因で走れなくなったらスピード持久が足りない、フォームが保てなくなったら体幹が足りない、設定タイムより速すぎたり遅すぎたりしてしまったら出力コントロール力が足りないなど、ベストを出すために必要なことを教えてくれます。
さあ、大会と同じ心持ちで、最高の準備をして今の力を思う存分発揮しましょう!
1月22日
荒川コーチの冬季練習のメイン練習を公開します(これを週1やりそれ以外の日は他の練習をしています)。
これは冬季の軸となる練習で、時期に応じて要素を少しずつ足しながら速度に変改していくことで、フィジカル・テクニックを充実させながらもケガ無くシーズンに入ることができます。
参考にしてみてください。
1月15日
末續さんがEAGLERUN RCに来てくれました!
末續さんに走りを見てもらい、また末續さんの指導も受けられ、かなり特別な時間でした。
こんなに年齢層も広く、レベルも様々で、何より高い熱度で人が集まる場所は日本でもなかなかないと思います。
それもそのはず、僕たちは末續さんとともに、普通のクラブではなく、唯一無二のクラブを一緒に作ってきました。
皆さんが、自分のこのクラブを誇りに思えるような、そんな場所をこれからも作っていきたいと思います。

1月8日
さあ2026年です!
年を経ることに、どんどん私の理論も変化しています。
もちろん軸となる部分は変わらないので、これまでのものの反対になるような変化はまずないのですが、知識の幅と奥行きがどんどん増えていき、指導や自分の練習にも変化が出てきています。
人間の体とはおもしろいもので、どれだけ素晴らしい練習でも同じものを繰り返していると体が順応しすぎてそれ以上伸びなくなります。
だからこそ、3年前と同じことをやっているようでは、以前のような結果はついてこないのです。
大事なのは、常に進化、深化させ続けること、そしてそれを求める姿勢です。
日曜は末續さんがついに来てくれます。
末續さんも以前より間違いなく進化しているので、皆の進化で新しい化学反応を生んでいきましょう!
12月30日
2025年のEAGLERUN RCが無事終了!
今年も1年本当にお疲れさまでした!
走るという共通の趣味趣向を持った人たちが集まり、世代を超えて活動を共にできること、改めて考えても本当にご縁だと思います。
世間的に言えば子どもにとっては大人たちと活動する機会は少なく、大人たちからすれば本気の背中を子どもたちに見せる機会は意外と多くありません。
だからこそ、この集団の中で得られるものは大きな財産になります。
挑戦は結果が大事です。
でもその結果を出したときにどう感じるかは、そこまでのプロセスが大事。
それはどれだけ頑張ったかということだけでなく、如何に心も満たし進めるか…
結果が心を満たすのではなく、プロセスで積み上げた経験が、つながりが、そして感受性が、その感動の深さを決めるのです。
だからこそ、僕たちは良い意味でこのままで、そしてさらに先を一緒に見ていきましょう!
今年もありがとうございました!

12月25日
21日に荒川コーチの練習挑戦会を行いました。
この目的は、トップ選手たちの練習のキツさを体験することではありません。
確かにキツい部分もありますが、日本ではキツい練習=いい練習という勘違いが多いのも事実なので、「何を考えてどう工夫することで練習効果を最大化しているのか?」を体験してもらうことが大事。
結局のところ、結果の差を生み出すのは日々のこだわりであり、効果を最大化させるためにどれだけ徹底できるかになります。
設定タイムや休憩時間、セット数、距離、心拍数など、全て理由を持って設計されることで主観に頼らない練習を作り上げています。
特に冬は工夫の差が大きく出やすいので「ただきつかった」ではなく、その先を見ていきましょう!
12月18日
12月も残りわずか。
皆さんは今年どんな1年でしたか?
来年への目標を定め、年始の初詣に向かう人も多いはず。
陸上競技は正しい努力が結果につながる、その意味でとてもやりがいのある競技です。
他のスポーツでは、どれだけ頑張っても相手が誰になるかなど運の要素も入ります。
ですが陸上は運の要素が限りなく少ないので、正しい努力が報われやすい競技です。
ただこの『正しい努力』が重要で、正しいとは確実な変化の伴う改善や向上が行えているということ。自己満足の努力では意味がありません。
動きであれフィジカルであれ、数値レベルで何かが良くなる、その結果としてタイムの向上が起こります。
例えば能力測定会のスピードスキップの数値が良くなった、新しいバウンディングができるようになった、など。
もし結果が出なければ、『ちゃんと変わっていたか?』を自問しなければならず、ちゃんと向き合える人が大きく成長します。
なので、今年は何を変えられたか、変えられなかったか、来年はそれらをどうしたいか、一つ深いレベルで振り返りと目標の設定をしてみましょう!
12月11日
今日は動きの変化が走力に変わるプロセスの話です。
僕たちは、新しい技術を手に入れれば急に速くなると期待しがちです。
残念ながら陸上では多くの場合そうはなりません。
なぜなら技術が上がっても、以前まで長きにわたりやってきた動きやその癖、またそれによって『その技術に合うように』適応した体や筋力はそのままだからです。
私も実はこれで失敗しており、今年末續さんとの技術共有もあり可動域を活かす新しい走りを会得できました。
ただ体が動くがゆえに、すぐにそれで記録を狙いにスピードを出しに行った結果、4月にケガをしてしまい9月まで約半年走れなくなりました。
なので、新しい走力を手に入れるには、以下の流れをたどります。
①正しい動き・技術を身に着ける(可動域含む)
②その動きで少し出力を落として何度も走りやドリルを反復する
③2か月くらいで新しい動きに適応した体や筋肉構造に変わってくる。
④そこから出力を徐々に上げ、未知のスピードへ
なので、新しい動きや技術を手に入れてから、適応するまでのステップを作ることが大事で、これが完了するまでは2か月かかるわけです。
その意味で冬季はこれをやるのに最も適した時期といえます。
まずは今EAGLERUN RCでやっている新しい動きや技術を早々に理解し、時間をかけて体にフィットさせていきましょう!
12月4日
日曜にERC記録会を行いました。
時期的には気温も下がり、体も冬仕様に変わるので少しタイムは出にくいものの、今年のまとめとしては非常に有効です。
大事なのは、タイムが変わるのは必ず理由があるということ。
僕たちは末續さんがオーナーを務め、世界基準の練習をかみ砕いて内容に落とし込んでいます。
しかし、練習の効果を決めるのは、結局は本人の理解度と繊細さ次第。
ただ形を真似するだけでなく、その目的や論理を理解し、正しい意識で確実に自分に落とし込むことができれば、どこよりも結果がついてくるチームだと思います。
是非、「これで合ってますか?」「ちょっと見てください。」とコーチをどんどん頼ってください。
一緒に陸上IQを高めながら、合理的に自分の最大値を出しに行きましょう!